再生医療心臓治療
再生医療心臓の基礎技術とiPS細胞活用
心臓は人体の中で最も再生能力が低い臓器の一つとして知られており、心筋梗塞などによって失われた心筋細胞は自然に回復することがありません。この根本的な問題を解決するため、iPS細胞(人工多能性幹細胞)を活用した心臓再生医療が注目を集めています。
iPS細胞から心筋細胞を作製する技術は急速に進歩しており、理論的に体を構成するすべての細胞へと分化できる能力を持つiPS細胞の特性を活かして、機能的な心筋細胞を効率的に生成することが可能になっています。従来の筋芽細胞や骨髄幹細胞による治療と比較して、iPS細胞は実際に失われた心筋細胞を補充できるため、より高い治療効果が期待されています。
2025年には京都大学の研究グループがヒトiPS細胞から機能的な成熟心外膜を効率的に生成する新手法を確立し、mTORシグナル伝達の抑制が心外膜の成熟と休止期状態を誘導する鍵であることを解明しました。この成果により、心臓の発達と修復における重要なメカニズムが明らかになり、心臓再生を促す新たな薬剤候補の同定も可能になっています。
現在の心不全治療では、症状の軽い患者には薬物療法が行われ、重症の場合は人工心臓や心臓移植が選択されますが、人工心臓には感染や脳梗塞のリスクがあり、心臓移植にはドナー不足という深刻な問題があります。再生医療は、薬物治療をすべて行っても症状が改善しない患者や人工心臓・心臓移植の適応になる手前の患者に対して、新たな治療選択肢を提供しています。
再生医療心臓の臨床応用と治験進行状況
日本国内では複数の機関でiPS細胞を用いた心筋再生治療の臨床治験が活発に進行しています。信州大学医学部附属病院循環器内科では、2024年8月から虚血性心疾患による重症心不全の患者を対象とした「iPS細胞を用いた心筋再生の治験」を開始しており、LAPiS試験として国内展開が図られています。
この治験に先立って実施された前臨床試験では、臨床治療用のヒトiPS細胞から作製した心筋細胞を心筋梗塞を発症させたカニクイザルの心臓に移植する実験が行われ、細胞移植を受けたサルの心機能回復に成功しています。さらに注目すべき点として、従来の報告と比較して心筋細胞移植後に発生する心室性不整脈の副作用が格段に少ないことが明らかになりました。
2025年4月には大阪大学発のベンチャー企業「クオリプス」が、iPS細胞から心臓の筋肉細胞を作り、厚さ0.1ミリのシート状に加工した「心筋細胞シート」について、厚生労働省に製造・販売の承認申請を行ったことが報告されています。企業によると、国に承認されればiPS細胞を使う治療としては世界初とみられ、今後の審査結果が注目されています。
京都大学の研究では、ヒトiPS細胞から誘導した心筋細胞や血管細胞から細胞シートを作製し、動的トレーニング培養を加えることによって血管構造を持つ「血管化心臓組織」を作製する技術が開発されています。この人工的な心臓組織をブタの心筋傷害モデルに移植した実験では、心表面マッピング法による電気生理学的評価により、伝導障害の改善効果が実証されています。
再生医療心臓移植技術の革新的手法
心臓再生医療において特に注目されるのが、従来の移植手術とは異なる革新的なアプローチです。慶應義塾大学医学部名誉教授の福田恵一氏は30年にわたる研究の結果、心臓の筋肉細胞を培養する技術を確立し、さらに「出血しない注射針」を独自開発することで、細胞移植手術の安全性を大幅に向上させています。
この技術により、従来の大がかりな外科手術を必要とせず、より低侵襲な方法で心筋細胞を患者の心臓に移植することが可能になっています。注射針による移植手法は、患者への身体的負担を軽減し、術後の回復期間短縮や合併症リスクの低減につながることが期待されています。
研究グループは、iPS細胞から作製した心筋細胞をブタの心筋障害モデルに移植し、心筋障害に起因する電気信号の伝わりにくさ(伝導障害)が改善されることを確認しています。組織移植群では移植1週間後に心筋障害部位での伝導速度が対照群よりも速くなることが確認され、心筋障害部位においてより多くの心筋組織が残存していることが伝導障害の改善につながったと考えられています。
心臓全体の再生に向けた取り組みも世界で進められており、動物の心臓から心筋細胞を取り出し、心臓の鋳型を作り、その鋳型にiPS細胞から作った心筋細胞をつけることにより、心臓の形をしたバイオ人工心臓を作成する研究が行われています。この技術が実用化されれば、ドナー不足で困窮する心臓移植の代替手段として大きな期待が寄せられています。
再生医療心臓の細胞分化メカニズム解明
心臓再生医療の発展には、細胞分化のメカニズム解明が不可欠です。2025年の京都大学CiRAの研究では、mTORシグナル伝達の抑制が心外膜の成熟化における重要な役割を果たすことが明らかになりました。心外膜は心臓を覆う膜組織であり、心臓の発達や修復において重要な機能を担っています。
研究グループは胎児型の心外膜について、細胞の増殖などに関わるタンパク質の働きを止めることで成人に近い膜を作製できることを発見しました。この成熟心外膜モデルを活用したスクリーニングにより、心臓再生を促す新たな薬剤候補を同定し、心臓病治療薬の開発を加速させることが可能になっています。
従来のiPS細胞から分化誘導された心筋細胞は胎児型の特徴を示すことが多く、成人の心筋細胞と比較して機能や構造に差異がありました。しかし、最新の研究により生物学的戦略を用いて心筋細胞の成熟化を促進する手法が開発され、より成人の心筋に近い機能を持つ細胞の作製が可能になっています。
心筋細胞の分化過程では、心筋収縮に必要なタンパク質の発現パターンや細胞内構造の形成が重要な要素となります。最新の研究では、培養環境の最適化や成長因子の適切な添加により、iPS細胞由来心筋細胞の収縮力や電気的特性を成人レベルに近づけることが可能になっています。これらの技術的進歩により、移植後の生着率向上や治療効果の持続性改善が期待されています。
再生医療心臓のダイレクトリプログラミング応用
心臓再生医療の革新的アプローチとして注目されているのが、心筋ダイレクトリプログラミング技術です。この手法は、体内に既に存在する心臓線維芽細胞を直接心筋細胞に転換する画期的な技術で、iPS細胞を経由しない新しい治療戦略として期待されています。
筑波大学と慶應義塾大学の共同研究グループは、心筋リプログラミング遺伝子の発現を薬剤投与によって自由に制御できる新しい遺伝子改変マウスを開発し、心筋梗塞慢性期の線維芽細胞から心筋細胞が再生し、心機能が改善することを世界で初めて明らかにしました。
この技術の特筆すべき点は、線維化に関与する悪玉心臓線維芽細胞を善玉線維芽細胞に変化させ、梗塞巣の退縮を促すことです。心筋梗塞後の心臓では、失われた心筋細胞の代わりに線維組織が形成され、心機能の低下につながりますが、ダイレクトリプログラミングによってこの線維化を抑制し、機能的な心筋組織を再生することが可能になっています。
2024年には慶應義塾大学の研究で、収縮力の保たれた心不全(HFpEF)が心筋ダイレクトリプログラミングによって改善されることが報告されています。従来のHFpEF治療は薬物療法に限られていましたが、心臓線維芽細胞において心筋リプログラミング遺伝子の発現を薬剤投与によって制御することで、新たな治療可能性が示されました。
この手法の最大の利点は、幹細胞を用いない点にあります。iPS細胞を用いた従来の再生医療では、腫瘍形成の可能性や組織生着率の低さが課題となっていましたが、ダイレクトリプログラミングではこれらの問題を回避しながら、心臓線維芽細胞からの心筋再生と抗線維化作用の両面で心不全を改善させることができます。
将来的には、この技術を臨床応用することで、心筋梗塞による難治性心不全に苦しむ患者に対して、より安全で効果的な根本的治療を提供できる可能性があり、心臓移植を必要とする患者数の減少にも貢献することが期待されています。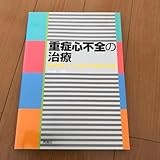
重症心不全の治療 : 補助循環・人工心臓・再生医療の実際
