ホットフラッシュの症状と原因から治療法
ホットフラッシュの症状の特徴
ホットフラッシュは更年期を迎える約6割の女性が経験する代表的な症状で、突然の身体の熱感や大量の発汗が特徴的です 。具体的には「身体がカーッと熱くなる」「涼しいのに汗が止まらない」「顔が赤くなる」「顔を中心に大量の汗をかく」といった症状が現れます 。
参考)https://www.fujiyaku-direct.com/health_information/article/100main
症状の持続時間には個人差があり、1回につき2~4分間ほど持続することもあれば、1時間程度の長時間にわたって悩まされることもあります 。特に50~54歳頃に症状が出やすく、この時期に症状も重くなりやすい傾向があります 。
日中の活動時や朝の起床時、夜の就寝前後に起こりやすく、夏や冬の季節、暖房が効きすぎた部屋などの環境要因も症状を誘発する要因となります 。
ホットフラッシュの原因とメカニズム
ホットフラッシュの根本的な原因は、加齢により卵巣機能が低下し、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量が急激に減少することです 。エストロゲンの分泌は脳の視床下部からの指令でコントロールされていますが、視床下部は体温調節や自律神経系も司る重要な器官でもあります 。
更年期に入ると視床下部からの指令に反してエストロゲンが分泌されなくなり、この機能障害が視床下部のほかの機能にも影響を及ぼします 。その結果、わずかな温度変化に過敏になったり、精神的ストレスを受けやすくなったりして、血管の急激な拡張によりホットフラッシュが発生するのです 。
脳の視床下部がエストロゲンの分泌を指示しても、閉経に向かって機能を縮小している卵巣はエストロゲンの分泌を増やすことができないため、視床下部がパニック状態となり自律神経のバランスが乱れます 。
参考)https://kamposhop.kracie.co.jp/shop/pages/chibakujiougan_hotflash.aspx
ホットフラッシュの治療法とホルモン補充療法
ホットフラッシュの治療において最も効果的とされるのが「ホルモン補充療法(HRT)」です 。HRTは減少したエストロゲンを経口剤(飲み薬)や経皮剤(貼り薬・塗り薬)で補充する治療法で、多くの患者が治療開始から数日~2週間ほどで「汗やほてりがなくなった」という効果を実感しています 。
参考)https://www.meno-sg.net/health/menopause/307/
ホルモン補充療法では、エストロゲン単独の使用で子宮からの出血や子宮体がんの発症率が高まることがあるため、それらのリスクを抑える黄体ホルモン(プロゲステロン)を併用したり、二つのホルモンの配合剤を使用します 。子宮摘出術を受けた方はエストロゲン単独の投与となります 。
治療開始前には検査を受けて疾患の有無を確認し、既往歴がある場合は適応を慎重に判断する必要があります 。症状が治まるまでの期間や夏場などの特定の季節のみHRTを行うという使い方も可能です 。
参考)https://todokusuri.com/column/post_20241113/
ホットフラッシュに効果的な漢方薬
ホットフラッシュの治療には漢方薬も効果的で、女性ホルモンを増やすわけではないため、子宮体がんや乳がんの既往がある方にも安心して使用できます 。漢方医学では、加齢や女性ホルモンとも関係のある「腎」のはたらきの低下や自律神経と関係のある「肝」が乱れることでホットフラッシュが起こりやすくなると考えます 。
多汗や強い肩こりなどがある人には「桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん)」が処方され、血の巡りを改善させる作用があります 。のぼせや興奮などがある人には「桃核承気湯(とうかくじょうきとう)」が更年期症状でよく処方される漢方薬です 。
参考)https://ena-nihonbashi.com/column/kounenki/2619/
腎に潤いを与えて余分な体の熱をとる瀉火補腎丸や杞菊地黄丸、亀鹿仙、気の流れを整える加味逍遥散や柴胡加竜骨牡蛎湯、抑肝散なども使用されます 。腎陽が不足する場合には八味地黄丸や海馬補腎丸、参茸補血丸、血行不良がみられる場合は婦宝当帰膠や芎帰調血飲などが用いられます 。
ホットフラッシュの予防と生活習慣での対策法
ホットフラッシュの予防には、日頃の生活習慣や食事内容に注意することで自律神経を整えることが効果的です 。
有酸素運動(ウォーキングや水泳、ジョギング)は副交感神経を優位にする働きがあるため、筋力トレーニングとして取り入れることでホットフラッシュ予防に効果が期待できます 。
参考)https://ena-nihonbashi.com/column/kounenki/2513/
食事面では、大豆製品の摂取がおすすめで、大豆には女性ホルモンに似た働きをもつイソフラボンが多く含まれています 。納豆1パックで65mg、無調整豆乳200mlで55mgのイソフラボンが摂取でき、1日あたりの摂取目安は70~75mgです 。ただし過剰摂取はホルモンバランスの乱れを引き起こす可能性があるため、摂取目安量を守ることが大切です 。
症状が出た際の対処法として、腹式呼吸が効果的で、交感神経が優位になりすぎることで起こる体温上昇や血管の収縮・血圧の上昇などの症状を緩和できます 。保冷剤などを使って顔や首を冷やすことで、太い血管がある首周りを冷やし、即座に冷えた血液を全身に巡らせることも有効です 。
参考)https://www.tamatani-clinic.com/blog/%E3%83%9B%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%95%E3%83%A9%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%81%A8%E3%81%AF%EF%BC%9F%E7%97%87%E7%8A%B6%E3%82%84%E5%8E%9F%E5%9B%A0%E3%80%81%E5%AF%BE%E7%AD%96%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%81%BE/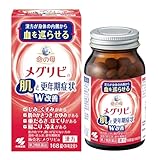
【第2類医薬品】メグリビa 168錠
