敗血症の治療
敗血症の病態と治療の基本概念
敗血症とは、感染症への生体反応が制御不能に陥り、生命を脅かす臓器機能障害を引き起こす臨床症候群です。この病態の理解は適切な治療戦略の立案に不可欠です。
敗血症の定義と分類 🎯
敗血症は感染により引き起こされる全身性炎症反応症候群(SIRS)を基盤とし、さらに重篤化すると敗血症性ショックに進展します。血圧低下、組織灌流障害、多臓器不全が特徴的な病態です。
敗血症の病態生理において重要な概念は、病原体関連分子パターン(PAMPs)と損傷関連分子パターン(DAMPs)による過剰な炎症反応です。これらの分子が免疫系を過度に活性化し、血管透過性亢進、血液凝固異常、微小循環障害を引き起こします。
治療の時間的制約 ⏰
敗血症治療における最も重要な要素は時間です。敗血症性ショックを疑った場合、認知から1時間以内の抗菌薬投与が強く推奨されています。この「ゴールデンアワー」を逃すことで、致死率が有意に上昇することが知られています。
日本における敗血症の死亡率は約30%と報告されており、適切な初期治療の重要性が強調されています。早期の診断と治療介入により、この死亡率を大幅に改善できる可能性があります。
敗血症の抗菌薬治療戦略
敗血症における抗菌薬治療は、診断確定前の経験的治療から始まり、培養結果に基づいた的確な治療へと段階的に進めていく必要があります。
経験的抗菌薬療法の選択 💊
初期治療では、想定される病原体を幅広くカバーする広域抗菌薬を選択します。重症度と感染部位に応じて以下のような選択肢があります:
- 軽症例:ABPC/SBT(スルバシリン)、CTRX(セフトリアキソン)
- 中等症〜重症例:PIPC/TAZ(タゾピペ)、MEPM(メロペン)
- MRSA疑い:バンコマイシン(VCM)併用
- 真菌感染疑い:アムホテリシンB、ミカファンギン併用
特に注意すべきは、ESBL産生菌や緑膿菌、嫌気性菌をカバーする必要がある症例です。患者の基礎疾患、入院歴、抗菌薬使用歴を詳細に聴取し、耐性菌のリスクを評価することが重要です。
de-escalation戦略 📉
培養結果が判明した後は、より狭域で的確な抗菌薬への変更(de-escalation)を行います。これにより薬剤耐性菌の出現抑制、副作用軽減、医療費削減が期待できます。
興味深い事例として、カプノサイトファーガ・カニモルサス感染症による敗血症では、軽微な動物咬傷歴でも重篤化することがあります。このような特殊な病原体に対しても、迅速な診断と適切な抗菌薬選択が予後を左右します。
培養検査と感受性試験 🔬
血液培養をはじめ、尿、喀痰、創部など複数部位からの検体採取を抗菌薬投与前に行うことが理想的です。近年では、集中治療室内での迅速診断システムにより、特殊染色や遺伝子検査を用いた病原菌の早期同定が可能になっています。
敗血症の循環管理と輸液蘇生
敗血症性ショックにおける循環管理は、組織への酸素供給を維持し、多臓器不全を防ぐための重要な治療戦略です。
初期輸液療法の実践 💧
循環血液量の減少に対して、生理食塩水30ml/kgを3時間以内に投与することが推奨されています。この初期輸液の効果判定には血清乳酸値の推移が重要な指標となります。
乳酸値の低下を目標とした輸液蘇生では、以下の手順で進めます。
- 初期輸液後の乳酸クリアランス評価
- 心エコーによる心機能・下大静脈(IVC)評価
- 輸液反応性の判定と追加輸液の必要性検討
血管作動薬の適応と選択 🫀
輸液蘇生にもかかわらず血圧が維持できない場合、血管作動薬の投与を検討します。第一選択薬はノルアドレナリンであり、平均動脈圧65mmHg以上を目標とします。
心機能低下がない場合の第二選択薬としてバゾプレッシンがあります。これらの薬剤選択には、心エコー検査による心機能評価が重要な判断材料となります。
ショック離脱の指標 📊
循環管理の成功指標として以下を評価します。
- 平均動脈圧の安定
- 尿量の改善(0.5ml/kg/時以上)
- 血清乳酸値の正常化
- 中心静脈酸素飽和度(ScvO2)の改善
特異的な症例として、飢餓性ケトアシドーシスを合併した敗血症では、従来の循環管理に加えてブドウ糖とインスリンの持続投与が必要になることがあります。高齢者における短期間の絶食と敗血症の組み合わせでは、このような病態を念頭に置いた治療が重要です。
敗血症の臓器サポート療法
多臓器不全を呈する敗血症患者では、各臓器機能を補完する支持療法が生命予後を左右する重要な治療となります。
呼吸管理とARDS対策 🫁
敗血症に伴う急性呼吸促迫症候群(ARDS)に対して、人工呼吸器による呼吸補助が必要になることがあります。肺保護戦略として、低一回換気量(6ml/kg)でのventilationが推奨されています。
重篤な症例では、体外膜酸素化(ECMO)の適応も検討されます。特にツツガムシ病による敗血症性ショックでは、ARDSや血球貪食症候群を合併することがあり、集学的な治療アプローチが必要です。
腎機能サポートと血液浄化 🩺
敗血症性急性腎障害に対して、持続的腎代替療法(CRRT)や血液透析による腎機能サポートを行います。血液浄化治療には腎機能代替以外にも、炎症性メディエーターの除去効果が期待されています。
ポリミキシンB固定化カラムによる直接血液灌流法(PMX-DHP)は、エンドトキシン除去を目的とした特殊な血液浄化療法です。標準治療で十分な効果が得られない重症敗血症患者に対する補助治療として位置づけられています。
代謝・内分泌管理 ⚗️
敗血症患者では血糖管理が重要であり、インスリンによる血糖コントロールが推奨されています。目標血糖値は180mg/dl未満とし、低血糖の回避に注意が必要です。
副腎不全を合併する症例では、ヒドロコルチゾンの補充療法が必要になることがあります。下垂体転移による中枢性副腎不全など、内分泌疾患の合併を見逃さないよう、反復した評価が重要です。
栄養療法とリハビリテーション 🍎
早期からの経腸栄養開始により、腸管バリア機能の維持と感染合併症の予防を図ります。また、ICU-AW(ICU-acquired weakness)の予防として、早期離床とリハビリテーションの導入が推奨されています。
敗血症治療における多職種連携と予後改善策
敗血症治療の成功には、医師・看護師をはじめとする多職種によるチーム医療が不可欠です。集中治療における包括的なアプローチが患者の生命予後と社会復帰に大きく影響します。
エビデンスに基づいた治療プロトコル 📋
日本版敗血症診療ガイドライン2020に基づく標準化されたプロトコルの実践により、死亡率と入院期間の短縮が実証されています。施設内での敗血症診療チームの構築と、定期的な症例検討会の開催が治療成績向上の鍵となります。
治療プロトコルには以下の要素が含まれます。
- バイタルサイン・意識状態の継続モニタリング
- 1時間毎の詳細な全身状態評価
- 血液ガス分析、乳酸値、電解質の頻回測定
- 腎機能、肝機能の経時的評価
合併症予防と長期予後管理 🛡️
敗血症は回復に時間を要する疾患であり、治療中の合併症予防が重要です。せん妄の予防と早期発見、深部静脈血栓症の予防、人工呼吸器関連肺炎の防止など、多角的なアプローチが必要です。
長期的な視点では、post-intensive care syndrome(PICS)の予防も重要な課題です。身体機能、認知機能、精神機能の包括的な評価とリハビリテーションにより、社会復帰支援を行います。
感染制御と院内感染対策 🦠
敗血症患者の治療過程では、医療関連感染の予防が極めて重要です。中心静脈カテーテル、尿道カテーテル、人工呼吸器などのデバイス関連感染の予防策を徹底します。
また、多剤耐性菌による敗血症では、適切な隔離予防策の実施と、院内感染制御チーム(ICT)との連携が不可欠です。抗菌薬適正使用支援チーム(AST)との協働により、適切な抗菌薬選択と使用期間の最適化を図ります。
質的向上と継続的改善 📈
敗血症診療の質的向上のため、診療指標の設定と定期的な評価が重要です。早期抗菌薬投与率、血液培養採取率、初期輸液完遂率などの指標により、施設の診療レベルを客観的に評価できます。
症例レビューと死亡症例検討会により、診療上の問題点を抽出し、継続的な改善サイクルを構築することで、敗血症診療の標準化と質の向上を実現できます。多施設共同研究への参加により、最新のエビデンス創出にも貢献することが期待されています。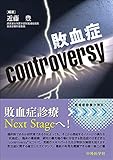
敗血症controversy
