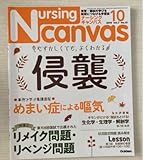嘔気の病態生理と分類
嘔気(おうき)は「吐きたい」という不快な感覚で、悪心(おしん)とも呼ばれます 。必ずしも嘔吐を伴うとは限らず、嘔気単独で出現することも珍しくありません 。嘔吐は胃の内容物が強制的に口から外へ排出される現象で、これらは似ていますが起きる仕組みが少し異なります 。
参考)https://uonc.jp/nausea.html
嘔気・嘔吐の発症原因は、大きく分けて中枢性嘔吐と末梢性(反射性)嘔吐に分類されます 。悪心を伴わない突然の嘔吐は、中枢性嘔吐を考慮しなければなりません 。嘔吐中枢は延髄という脳の一番下の部分に存在し、この部位は血液脳関門に覆われているため、直接催吐性の物質には反応しませんが、神経を介した入力を受けます 。
参考)https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/kochi/20140325001/oshinouto.pdf
嘔気の神経伝達メカニズムと受容体
嘔吐中枢への入力には4つの主要な経路があります 。大脳皮質からの入力では、精神的あるいは感情的な要因によっても嘔吐が起こり、化学療法における予期性嘔吐がその例です 。神経伝達に関与する受容体として、ドパミンD2受容体、ムスカリン受容体、ヒスタミンH1受容体、セロトニン5HT2,3受容体、ニューロキニンNK1受容体などがあります 。
参考)https://www.jspm.ne.jp/files/guideline/gastro_2011/02_01.pdf
化学受容器引金帯(CTZ)は血液脳関門の外にあるため、血中の化学物質に直接反応します 。抗がん剤により小腸の腸クロム親和性細胞からセロトニンが分泌され、神経にあるセロトニン(5HT-3)受容体に結合し、CTZを経て嘔吐中枢を刺激します 。
参考)https://oici.jp/file/recipe/202103/symptom7-02.pdf
嘔気を引き起こす消化器系疾患
胃腸炎は嘔気・嘔吐の最も一般的な原因の一つです 。ウイルス性腸炎の典型的な症状および経過は、まず「嘔気」「嘔吐」から始まり、続いてみぞおち周辺の「腹痛」、そして水様性の「下痢」という順序で現れます 。通常の経過としては「吐き気→発熱や腹痛→下痢」になってくることが多いです 。
参考)https://www.msdmanuals.com/ja-jp/home/03-%E6%B6%88%E5%8C%96%E5%99%A8%E7%B3%BB%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97/%E6%B6%88%E5%8C%96%E5%99%A8%E7%B3%BB%E3%81%AE%E7%97%85%E6%B0%97%E3%81%AE%E7%97%87%E7%8A%B6/%E6%88%90%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%90%90%E3%81%8D%E6%B0%97%E3%81%A8%E5%98%94%E5%90%90
急性胃炎・慢性胃炎、胃潰瘍・十二指腸潰瘍、胃がん、逆流性食道炎、感染性腸炎、腸閉塞、虫垂炎なども嘔気の原因となります 。腸閉塞では腸管が詰まり、吐き気や激しい嘔吐を引き起こし、吐物に便が混ざることもあります 。
参考)https://www.onuki-clinic.com/nausea/
嘔気の中枢神経系および全身性原因
脳梗塞、脳出血、髄膜炎、脳炎などの脳神経系の疾患でも吐き気や嘔吐が起こることがあります 。聴神経腫瘍では術後に回転性めまいや嘔吐が出現する場合があり、手術で小脳を触るため、小脳症状としてめまい、吐き気、食欲不振が出ることもあります 。
参考)https://www.ichou.com/nausea/
狭心症・心筋梗塞では典型的な胸痛がなくても、吐き気、嘔吐、歯痛、左肩痛などの症状が現れることがあります 。また、妊娠、乗り物酔い、糖尿病などの全身性疾患、精神疾患も嘔気の原因となります 。
参考)https://www.saiseikai.or.jp/medical/symptom/nausea/
嘔気の薬剤性要因と抗がん剤治療
多くの物質が吐き気と嘔吐を引き起こす可能性があり、アルコール、オピオイド鎮痛薬、大麻、化学療法薬が含まれます 。薬剤性嘔気・嘔吐とは、薬の副作用によって起こる吐き気や嘔吐のことです 。
参考)https://ubie.app/byoki_qa/clinical-questions/eqtiz-60r03
抗がん剤による吐き気・嘔吐は、急性嘔吐(治療開始直後から24時間後まで)、遅発性嘔吐(治療開始後24時間から48時間頃から起こり2日から5日くらい続く)、予測性嘔吐(抗がん剤治療で吐いた記憶から生じる嫌悪感による)の3種類に分けられます 。催吐性リスク分類では、制吐薬の予防投与無しで各種抗癌剤投与後24時間以内に発症する悪心・嘔吐の割合に従い、高度、中等度、軽度、最小度の4つのカテゴリーに分類されます 。
参考)https://www.ncc.go.jp/jp/ncce/division/pharmacy/kouganzai/supportivecare_antiemetic.html
嘔気の独創的な治療アプローチと予防法
従来の制吐療法に加えて、近年注目されているのが統合医療的アプローチです。漢方医学では、食物をとったあとの消化吸収は胃と脾が協力しあって行い、肝がその調節に関与していると考えます 。胃気が逆に上方に向かってしまう(上逆)ために嘔気が生じるとされ、この概念は現代医学の嘔吐中枢理論と興味深い相関を示しています。
参考)https://www.fureaikanpou.com/post/2019/02/05/%E5%90%90%E3%81%8D%E3%81%91%E3%83%BB%E5%98%94%E5%90%90
抗精神病薬(オランザピン)を用いた新しい制吐療法では、用量を減らし内服時間を工夫することで、副作用を抑えながら現在の標準的な制吐療法よりも高い悪心・嘔吐抑制効果が得られることが確認されています 。遅発期(抗がん剤開始から2〜5日目)の嘔吐完全抑制割合を13%改善する成績が報告されています 。
参考)https://www.scchr.jp/press/%E6%8A%97%E3%81%8C%E3%82%93%E5%89%A4%E6%B2%BB%E7%99%82%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E6%82%AA%E5%BF%83%E3%83%BB%E5%98%94%E5%90%90%E3%81%AE%E6%96%B0%E3%81%97%E3%81%84%E5%88%B6%E5%90%90%E7%99%82%E6%B3%95.html
日常生活での対処法として、安静にして十分な休息をとり、深呼吸やストレッチ、瞑想などのリラクゼーション法が有効です 。食事では少量の消化の良い食事を何回かに分けて摂り、乾燥した食品や白米、トースト、バナナなどの消化を助ける食品がおすすめされます 。