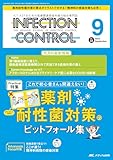薬剤耐性菌と現代医療の課題
薬剤耐性菌は、抗菌薬(抗生物質)に対して耐性を獲得した細菌の総称です 。WHO(世界保健機関)の推計によると、2019年の1年間に薬剤耐性菌が原因の感染症で亡くなった人の数は全世界で100万人を超えており、対策が急務となっています 。これらの細菌は通常の細菌と比べて病原性が高いわけではありませんが、高齢者、乳幼児、免疫力の低下した患者では重篤な感染症を引き起こすことがあります 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11764262/
薬剤耐性のメカニズムは非常に複雑で、細菌は様々な戦略を用いて抗菌薬から身を守ります 。主要な耐性機序として、薬剤分解酵素の産生があり、MRSAはペニシリナーゼやβラクタマーゼという酵素を産生してペニシリン系やセフェム系薬剤を分解します 。また、細菌が自身の膜構造を変化させて薬剤の流入を防ぐ「外膜変化」や、取り込んだ薬剤を細胞外に排出する「排出ポンプ」も重要な耐性機序です 。
参考)https://pro.saraya.com/sanitation/column/kobayashi/
近年特に問題となっているのは、複数の抗菌薬に同時に耐性を持つ多剤耐性菌(MDR)の出現です 。これらの細菌により、従来有効であった治療選択肢が次々と失われ、治療困難な感染症が増加しています。イギリスの報告書では、十分な対策が行われない場合、2050年までに薬剤耐性菌による死者数ががんによる死者数を上回る可能性があると警告されています 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10397562/
薬剤耐性菌MRSA感染症の臨床的特徴
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)は、最も重要な薬剤耐性菌の一つです 。MRSAは、ペニシリン系だけでなく、セフェム系、カルバペネム系、ニューキノロン系、アミノグリコシド系など多剤に耐性を示します 。以前は主に院内感染の原因菌として問題でしたが、現在では市中での感染事例も増加しており、地域レベルでの対策が必要となっています 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9055366/
MRSAによる感染症は、皮膚・軟部組織感染症から敗血症まで幅広い病態を呈します。特に免疫機能が低下した入院患者では、肺炎や心内膜炎などの重篤な感染症を引き起こすことがあり、死亡率も高くなります。治療には、バンコマイシンやテイコプラニンなどのグリコペプチド系抗菌薬が使用されますが、これらの薬剤に対する耐性菌(VRSA)の出現も報告されており、治療選択肢がさらに限られる状況が懸念されています 。
参考)https://janis.mhlw.go.jp/section/standard/drugresistancestandard_ver3.3_202402.pdf
日本の厚生労働省院内感染対策サーベイランス(JANIS)のデータでは、MRSAの検出率は医療機関により大きく異なりますが、依然として重要な監視対象となっています 。感染制御の観点からは、標準予防策の徹底と接触予防策の適切な実施が不可欠です。
参考)https://amr.jihs.go.jp/medics/2-2-1.html
薬剤耐性菌ESBL産生菌の拡散と対策
基質特異性拡張型β-ラクタマーゼ(ESBL)産生菌は、第3世代・第4世代セフェム系抗菌薬に耐性を示す重要な薬剤耐性菌です 。肺炎桿菌、大腸菌、Klebsiella oxytoca、Proteus mirabilisなどから検出されることが多く、以前は院内感染の原因菌として問題でしたが、現在は市中にも広く定着しつつあります 。
参考)https://amr.jihs.go.jp/medics/2-1-3.html
ESBLはAmbler分類でClassAβ-ラクタマーゼに属し、本来ペニシリン系抗菌薬を分解する酵素でしたが、遺伝子変異により基質特異性が拡張され、より広範囲のβ-ラクタム系抗菌薬を分解するようになりました 。このため、従来有効であった第3世代セフェム系抗菌薬(セフトリアキソン、セフタジジムなど)が無効となり、治療選択肢が大幅に制限されます。
参考)http://www.med.kagawa-u.ac.jp/~mrsa/infection_control/manual/pdf/4_3.pdf
ESBL産生菌の治療には、従来カルバペネム系抗菌薬が第一選択とされてきました 。しかし、カルバペネム系抗菌薬の使用増加に伴い、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)の出現が新たな問題となっています 。このため、ESBL産生菌に対してもカルバペネム系抗菌薬以外の治療選択肢の検討が重要となっており、セフタロリンやセフトロザンなどの新規抗菌薬の開発が進められています。
参考)https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000189816.pdf
感染制御の面では、ESBL産生菌も接触予防策の対象となります 。特に尿路感染症や腹腔内感染症の原因となることが多いため、排泄物やおむつの取り扱いには十分な注意が必要です。
参考)http://www.kankyokansen.org/other/edu_pdf/3-3_10.pdf
薬剤耐性菌カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の脅威
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE)は、最も危険度の高い薬剤耐性菌の一つです 。カルバペネム系抗菌薬は極めて広範囲の細菌に効果があり、薬剤耐性菌に対する最後の砦とされてきましたが、CREの出現により、この治療選択肢も脅かされています 。
CREの耐性機序は多様で、カルバペネム系抗菌薬を分解する各種カルバペネマーゼの産生、AmpCやESBLの過剰産生、膜透過性(ポーリン)の低下などが関与しています 。特にカルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌(CPE)は、最も注意すべき薬剤耐性菌として位置づけられており、医療機関では最高レベルの感染対策が要求されます 。
参考)https://www.hosp.med.osaka-u.ac.jp/home/hp-infect/file/manual/e-1.pdf
世界的には、NDM(New Delhi Metallo-β-lactamase)、KPC(Klebsiella pneumoniae carbapenemase)、OXA-48などの様々なカルバペネマーゼが報告されており、地域により優勢な酵素が異なります 。これらの酵素遺伝子はプラスミドに存在することが多く、細菌間での水平伝播により急速に拡散する特徴があります。
CRE感染症の治療は極めて困難で、コリスチンやチゲサイクリンなどの限られた薬剤に依存することが多く、副作用や治療効果の面で問題があります 。近年、セフタジジム/アビバクタムやメロペネム/バボルバクタムなどの新規抗菌薬が開発されていますが、これらに対する耐性菌の出現も既に報告されており、継続的な監視が必要です。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9668277/
薬剤耐性菌に対する新たな治療戦略
従来の抗菌薬が無効な薬剤耐性菌に対して、革新的な治療アプローチが研究されています。
バイオフィルムは細菌が形成する特殊な構造体で、薬剤耐性の重要な要因となっています 。バイオフィルム内の細菌は通常の浮遊状態の細菌より数百倍も抗菌薬に対する耐性が高く、慢性感染症の原因となることが多いです 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7465149/
最新の研究では、バクテリオファージ(細菌を攻撃するウイルス)を利用した治療法が注目されています 。ファージは薬剤耐性菌を特異的に標的とし、バイオフィルムを破壊する能力も持っています。韓国科学技術院とイリノイ大学の共同研究では、マイクロバブルと遺伝子標的ナノ粒子を組み合わせた新しい治療法が開発され、MRSAのバイオフィルム形成遺伝子、細胞分裂遺伝子、抗生物質耐性遺伝子を同時に阻害することに成功しています 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11487266/
ナノテクノロジーを応用した治療法も有望です 。沖縄科学技術大学院大学では、銀ナノ粒子とアジスロマイシンを組み合わせたコアシェル構造の新規製剤を開発し、表皮ブドウ球菌のバイオフィルムに対して従来の1.5倍の抗菌効果を示すことを確認しています 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10521699/
また、物質・材料研究機構の研究では、緑膿菌の生命活動レベルを精密に測定する新技術により、バイオフィルム状態で活動が通常の1000分の1以下に低下した細菌でも、細胞膜に作用するタイプの抗菌薬は効果を示すことが判明しました 。これらの知見は、新しい抗菌薬開発の方向性を示す重要な成果となっています。
参考)https://www3.nhk.or.jp/news/html/20241231/k10014682891000.html
薬剤耐性菌対策における抗菌薬適正使用の実践
薬剤耐性菌の拡散を防ぐためには、抗菌薬の適正使用が極めて重要です 。抗菌薬の不適切な使用は耐性菌の選択圧となり、耐性菌の増加を促進します 。適正使用の基本原則として、適切な抗菌薬を、適切な量で、適切な期間、適切な投与ルートで使用することが求められます 。
具体的な適正使用戦略として、抗菌薬事前許可制やフィードバックによる介入、薬物動態モニタリング、治療期間の最適化などがあります 。特に重要なのは、ウイルス感染症に対する不必要な抗菌薬処方を避けることです。感冒やインフルエンザなどのウイルス性疾患では抗菌薬は無効であり、患者や家族への適切な説明と理解が必要です 。
参考)https://www.azumien.jp/contents/industry/00134.html
De-escalationは、初期治療で広域スペクトラム抗菌薬を使用した後、原因菌が判明次第、より狭域で適切な抗菌薬に変更する戦略です 。これにより治療効果を維持しながら、不必要な広域抗菌薬の使用を避けることができます。また、処方された抗菌薬は医師の指示通りに最後まで服用することが重要で、自己判断での中断は耐性菌発現のリスクを高めます 。
医療機関では、感染制御チーム(ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(AST)が連携して、薬剤耐性菌対策に取り組んでいます。これらのチームは前向き監視とフィードバック、院内ガイドラインの整備、教育研修の実施などを通じて、適正使用の推進と耐性菌の制御を図っています 。