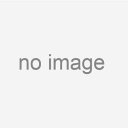アゴニストとリガンドの違い
アゴニストとリガンドの基本概念
リガンドとは、受容体に特異的に結合する物質の総称です。生体内に元々存在する神経伝達物質やホルモンなどの内因性リガンドと、外部から投与される薬物などの外因性リガンドが含まれます。リガンドという用語は、受容体との結合能力に着目した広範な概念であり、その結合後にどのような機能的変化が起こるかは問いません。
netdekagaku+3
一方、アゴニストは受容体に結合して受容体を活性化し、生理的反応を誘発する物質を指します。日本語では「作動薬」または「刺激薬」と呼ばれ、受容体との結合によって細胞内のシグナル伝達を開始させる機能を持ちます。アゴニストはリガンドの一種ですが、すべてのリガンドがアゴニストとして機能するわけではありません。
wikibooks+3
両者の関係を整理すると、リガンドは受容体結合能を持つ物質全体を指す構造的・化学的な分類であり、アゴニストは受容体を活性化する機能を持つリガンドの機能的分類です。元来、生体内物質を「リガンド」、外来物質を「アゴニスト」と厳密に区別する場合もありましたが、現在では両者は同義語として扱われることが多く、由来を明確にする際は「内因性リガンド」「外因性アゴニスト」のように表現されます。
ebn2.arkray+2
アゴニストの種類と受容体活性化メカニズム
アゴニストは受容体に対する活性化の程度によって複数のタイプに分類されます。フルアゴニスト(完全作動薬)は受容体を最大限に活性化し、内因性リガンドと同等またはそれ以上の生理的反応を引き起こします。受容体の全ての結合部位を占有した際に最大反応を示すため、用量反応曲線では最大効果に到達します。
msdmanuals+2
パーシャルアゴニスト(部分作動薬)は、受容体に結合しても部分的な活性化しか引き起こさず、フルアゴニストよりも弱い反応を示します。興味深いことに、フルアゴニストが存在する環境下では、パーシャルアゴニストはアンタゴニストのように抑制的に作用します。統合失調症治療薬のアリピプラゾールやブレクスピプラゾールは、ドパミンD2受容体のパーシャルアゴニストとして機能し、ドパミンの活動が過剰な部位では抑制的に、不足している部位では刺激的に働きます。
webview.isho+2
インバースアゴニスト(逆作動薬)は、リガンドが存在しなくても一定の自発的活性を持つ受容体の活性を低下させます。ヒスタミンH1受容体は活性型と不活性型が動的平衡状態にありますが、インバースアゴニストは不活性型受容体を安定化させることで受容体全体の数を減少させます。この作用により、花粉症の初期治療で使用すると、花粉飛散時のアレルギー反応を軽減できます。
nagatomo-ent+2
受容体活性化のメカニズムとして、リガンドが受容体の細胞外部分に結合すると、細胞膜を貫通する領域の立体構造変化や回転が誘発され、細胞内部のシグナル伝達が開始されます。この過程では受容体タンパク質の柔軟性も変化し、リガンド結合前は細胞外部分の柔軟性が高く細胞内部分は安定していますが、結合後はその逆になります。
eurekalert
受容体とリガンドの複合体構造モデリングに関する詳細な解説(J-STAGE)
アンタゴニストとリガンド結合の相互作用
アンタゴニスト(拮抗薬)は受容体に結合するものの、受容体を活性化せず、他のアゴニストの作用を阻害するリガンドです。日本語では「拮抗薬」「遮断薬」「ブロッカー」とも呼ばれ、アゴニストとは対照的な機能を持ちます。
wikipedia+1
アンタゴニストは作用機序により競合的拮抗薬と非競合的拮抗薬に分類されます。競合的拮抗薬はアゴニストと同じ結合部位(オルソステリック部位)で受容体と可逆的に結合し、濃度依存的にアゴニストの結合を妨げます。この場合、アゴニストの濃度を十分に高めれば、競合的拮抗薬の効果を克服して最大反応に到達できます。用量反応曲線では、競合的拮抗薬の存在下でアゴニストの曲線が右方向(高濃度側)へシフトしますが、最大反応は変化しません。
m-hub+1
非競合的拮抗薬はアゴニストとは異なる部位(アロステリック部位)に結合するか、受容体と不可逆的に結合します。この場合、アゴニストの濃度を増加させても拮抗作用を完全には克服できず、用量反応曲線では最大反応の低下が観察されます。NMDAグルタミン酸受容体を不可逆的に遮断する(+)-MK 801マレイン酸は非競合的拮抗薬の代表例です。
wikipedia+1
受容体とリガンドの結合は、水素結合、イオン結合、ファンデルワールス力、疎水性結合などの非共有結合によって成立します。この結合は特異的かつ可逆的であり、リガンドの化学構造が受容体の結合部位と適合することで選択性が生まれます。結合親和性(Kd値)が低いほど受容体への結合力が強く、少量で効果を発揮します。
cosmobio+3
受容体とリガンドの相互作用の詳細な解説(M-hub)
アゴニストの親和性と固有活性の臨床的意義
アゴニストが受容体に作用する能力は、親和性(affinity)と固有活性(intrinsic activity)の2つの特性によって規定されます。親和性とは、ある瞬間において薬物が受容体を占有している確率を示し、薬物と受容体の結合強度を表します。一方、固有活性は、リガンドが受容体に結合した後に細胞応答を誘導する強さを示します。
msdmanuals
興味深いことに、最大効果の50%を生じる薬物濃度(EC50)と受容体の50%を占めるために必要な薬物濃度(Kd)が一致しない現象が存在します。EC50がKdよりも小さい場合、予備受容体(spare receptors)が存在することを意味します。予備受容体とは、アゴニストが最大反応を示しても未占有のまま残る受容体のことです。
jove
予備受容体の存在により、細胞はホルモンや神経伝達物質などの内因性アゴニストを経済的に使用できます。単一のアゴニスト-受容体複合体が複数の下流エフェクター分子を活性化する経路では、すべての受容体が占有される必要はありません。また、アゴニスト-受容体複合体が解離した後も、活性化されたエフェクター分子が標的タンパク質を活性化し続けるため、一部の受容体のみで十分な効果が得られます。インスリン受容体では99%が予備受容体であり、これがインスリンレベルのわずかな変化に対する細胞の高い感受性を説明しています。
jove
薬物-受容体複合体の存続時間(滞留時間)も薬理作用に重要な影響を与えます。滞留時間が長いことは薬理作用が持続することを意味し、フィナステリドやダルナビルなどは滞留時間が長い薬物として知られています。ただし、薬物の毒性が長引く可能性もあるため、滞留時間が長いことが必ずしも有利とは限りません。
msdmanuals
臨床応用において、受容体の数や結合親和性は薬物、加齢、遺伝子変異、疾患などにより増加(アップレギュレーション)または減少(ダウンレギュレーション)します。長期的なアゴニスト刺激により受容体が細胞内に取り込まれて細胞膜上の受容体数が減少する現象(脱感作)は、薬物耐性の重要なメカニズムです。
gakkenshoin+1
薬物-受容体相互作用の臨床薬理学的解説(MSDマニュアル)
アゴニスト非依存的受容体活性化と構成的活性
従来、G蛋白質共役型受容体(GPCR)はアゴニストとの結合によってのみ活性化すると考えられてきましたが、近年の研究により、リガンドが存在しない状態でも自律的に活性を示す受容体の存在が明らかになっています。この現象は構成的活性(constitutive activity)または基底活性と呼ばれ、特にアンジオテンシンII 1型(AT1)受容体で顕著に観察されます。
astellas-foundation
構成的活性を持つ受容体は、活性型と不活性型の間で動的平衡状態を保っています。ヒスタミンH1受容体を例に取ると、リガンドが存在しない状態でも一定の割合で活性型受容体が存在し、内在性シグナル(basal signaling)を発現します。この内在性シグナルが細胞全体の受容体数の維持に関与しています。
sadanaga+1
AT1受容体は、アゴニスト非存在下でも自律的活性を示すだけでなく、伸展刺激というメカニカルストレスによっても活性化されます。このアゴニスト非依存的活性化は、心血管リモデリングの病態に深く関与しており、高血圧や心不全などの疾患の発症メカニズムを理解する上で重要です。
astellas-foundation
GPCRにおける受容体活性化モデルとして、リガンドが結合していない状態でも受容体は活性型と不活性型の平衡状態にあり、アゴニストは活性型への平衡を促進し、インバースアゴニストは不活性型への平衡を促進すると考えられています。アンタゴニストは両方の型と同程度の親和性で結合するため、平衡状態を変化させません。
jstage.jst
この概念は薬物設計において重要な意義を持ちます。アンタゴニストとインバースアゴニストは従来同じように扱われてきましたが、構成的活性を持つ受容体に対しては異なる効果を示します。臨床的には、インバースアゴニスト作用を持つ抗ヒスタミン薬を花粉飛散前から使用することで、受容体数を減少させ、花粉症の症状を予防的に軽減できることが示されています。
nagatomo-ent+1
アンジオテンシンII受容体のアゴニスト非依存的活性化に関する研究報告(PDF)
アゴニストとリガンドの臨床応用における選択性
臨床現場において、リガンドとアゴニストの選択性は治療効果と副作用のバランスを決定する重要な因子です。選択性とは、薬物が他の部位よりもある特定の受容体サブタイプに作用しやすい程度を示します。1つの受容体サブタイプだけに完全に特異的な薬物はほとんど存在せず、大半の薬物は相対的な選択性を有します。
msdmanuals
受容体サブタイプへの選択性を高めるためには、リガンドの化学構造を最適化する必要があります。カテコールアミン(ノルアドレナリン、ドーパミンなど)を例に取ると、カテコール環の部位が作用発現に必要な作用基であり、炭素鎖を持つアミンの部位が結合基です。作用基であるカテコール環に改変を加えるとアンタゴニストとして働く場合が多く、結合基に改変を加えると受容体サブタイプへの選択性や作用濃度域が変化します。
wikipedia
GPCRにおいてはリガンドの機能(アンタゴニスト、アゴニストなど)によって受容体の立体構造が異なるため、ホモロジーモデリングによる構造予測においてどのような受容体構造情報を用いるかが重要な課題となります。アンタゴニストやインバースアゴニストが結合する不活性構造の結晶構造と、アゴニストが結合した活性化状態の結晶構造では、受容体の立体構造が大きく異なります。
jstage.jst
ドパミンD2/D3受容体パーシャルアゴニストであるアリピプラゾール、ブレクスピプラゾール、cariprazineは、それぞれ異なる受容体プロファイルを持ちます。ブレクスピプラゾールはアリピプラゾールと比較してドパミンD2活性が低く、セロトニン5-HT1Aおよび5-HT2A受容体親和性が高い一方、cariprazineはドパミンD3受容体親和性が最も高く半減期も最も長いという特徴があります。このような受容体選択性の違いが、臨床効果や副作用プロファイルの相違をもたらします。
carenet+1
パーシャルアゴニストは、喫煙やアヘン中毒の治療に臨床的に使用されています。ブプレノルフィンやバレニクリンは、それぞれオピオイド受容体やニコチン受容体を部分的に活性化することで、脳が完全なアゴニストであるヘロインやニコチンを渇望するのを抑制します。
jove
ドパミン受容体パーシャルアゴニストの臨床比較(CareNet)