アポトーシスとネクローシス
アポトーシスの分子メカニズムと形態学的特徴
アポトーシスは、1972年にKerrらによって提唱された「プログラムされた細胞死」の代表的な様式であり、発生過程や組織の恒常性維持に不可欠な生理的現象です。この細胞死では、細胞の収縮、クロマチンの凝縮、核の断片化、そして細胞膜のブレッビング(budding)といった特徴的な形態変化が観察されます。最終的に、細胞は複数のアポトーシス小体へと断片化され、周囲のマクロファージによって速やかに貪食除去されるため、炎症反応を引き起こしません。
m-hub+3
アポトーシスは「内因性経路(ミトコンドリア経路)」と「外因性経路(死の受容体経路)」の2つの主要な経路を介して誘導されます。内因性経路は、DNA損傷、細胞ストレス、生存因子の欠如などにより活性化され、ミトコンドリア外膜透過化(MOMP)を引き起こします。その結果、サイトクロムcが細胞質に放出され、Apaf-1およびプロカスパーゼ-9と結合してアポトソームを形成し、カスパーゼカスケードが活性化されます。一方、外因性経路は、FasリガンドやTNF-αなどの細胞死リガンドが細胞表面のデスレセプターに結合することで開始され、カスパーゼ-8が直接活性化されます。
cellsignal+3
カスパーゼは、アポトーシスの実行において中心的な役割を果たすシステインプロテアーゼであり、細胞骨格タンパク質や核タンパク質を選択的に分解することで、アポトーシスの形態学的変化を引き起こします。カスパーゼファミリーは、開始カスパーゼ(カスパーゼ-8、-9、-10)と実行カスパーゼ(カスパーゼ-3、-6、-7)に分類され、厳密に制御されたカスケードを形成しています。
pmc.ncbi.nlm.nih+2
ネクローシスの特徴と病態生理学的意義
ネクローシスは、細胞が物理的・化学的損傷を受けた際に生じる偶発的な細胞死であり、アポトーシスとは対照的に分子機構による制御を受けません。虚血性疾患(脳梗塞、心筋梗塞)、外傷、ウイルス感染、毒素曝露などの外的要因により引き起こされます。ネクローシスでは、細胞は浸透圧の維持ができなくなり、急激に膨張して最終的に細胞膜が破裂します。
jstage.jst+4
細胞膜の破綻に伴い、high mobility group box 1(HMGB1)やATPなどのダメージ関連分子パターン(DAMPs)が細胞外に放出されます。これらのDAMPsは、周囲の細胞のパターン認識受容体に作用し、強い炎症反応を誘導します。この炎症反応は、さらなる組織損傷を引き起こし、周囲の健康な細胞にもダメージを与える可能性があります。このため、ネクローシスは「他を巻き込む死」とも表現され、組織修復を妨げる病態生理学的に重要な現象です。
meditlab+4
形態学的には、ネクローシスではクロマチンの凝縮、核の溶解(karyolysis)、細胞質の膨張が観察され、アポトーシスにみられる秩序だった断片化とは異なる特徴を示します。また、ネクローシス細胞においてもホスファチジルセリン(PS)が細胞表面に露出する場合があることが報告されており、細胞死の識別には複数のマーカーの評価が必要です。
jsth+2
ネクロプトーシスとアポトーシス・ネクローシスの関係
近年、「制御されたネクローシス」とも呼ばれるネクロプトーシスが注目を集めています。ネクロプトーシスは、2000年代に報告された新しい細胞死様式で、アポトーシスが阻害された環境において活性化される細胞防御機構です。形態学的にはネクローシスに類似し、細胞膜の早期破裂と炎症反応の誘導を特徴としますが、分子機構により厳密に制御されている点でアポトーシスとの共通性を持ちます。
cellsignal+4
ネクロプトーシスの主要な分子機構は、RIPK1(receptor-interacting protein kinase 1)、RIPK3、およびMLKL(mixed lineage kinase domain-like protein)により構成されるネクロソーム複合体の形成です。TNF-αなどの刺激により、RIPK1とRIPK3が相互作用してネクロソームを形成し、RIPK3がMLKLをリン酸化します。リン酸化されたMLKLは多量体化して細胞膜に移行し、膜にポアを形成することで細胞膜の崩壊と細胞破壊を引き起こします。このプロセスは、ネクロプトーシス阻害剤Necrostatin-1(Nec-1)によって特異的に阻害されることが知られています。
cellsignal+2
興味深いことに、カスパーゼ-8は、RIPK1およびRIPK3を切断することでネクロプトーシスを阻害する機能を持っています。このため、ウイルス感染などによりカスパーゼ-8が阻害された状況では、細胞はアポトーシスからネクロプトーシスへと細胞死様式を切り替えることができます。この柔軟な細胞死制御機構は、病原体排除における生体防御の重要な戦略であると考えられています。
cellsignal+3
ネクロプトーシスの個体での可視化技術に関する研究(東邦大学)
制御された細胞死であるネクロプトーシスの生体内での可視化技術について、最新の研究成果が報告されています。
アポトーシス検出における細胞膜PSの露出とマクロファージによる認識
アポトーシス細胞と生細胞を区別する最も重要な特徴の一つは、細胞膜上のホスファチジルセリン(PS)の分布変化です。通常、PSは細胞膜の内側に局在していますが、アポトーシスが開始されると、フリッパーゼ活性の低下とスクランブラーゼの活性化により、PSが細胞膜の外側に露出します。この「eat-me」シグナルとしてのPS露出は、マクロファージなどの貪食細胞表面の貪食受容体によって認識され、アポトーシス細胞の迅速な貪食除去を促進します。
mnc.toho-u+2
アポトーシス細胞を貪食したマクロファージは、炎症抑制因子を産生し、組織傷害を最小限に抑えます。この非炎症性の貪食除去機構は、正常な発生過程や組織のリモデリングにおいて極めて重要です。対照的に、アポトーシス細胞が適切に除去されずに二次的ネクローシスに至ると、細胞内容物が放出され、自己免疫疾患の発症リスクが高まります。
katosei.jsbba+2
アポトーシス細胞の認識には、PS以外にも糖鎖の変化やトロンボスポンジン(TSP)の関与が報告されています。アポトーシスが進行すると、糖鎖を持つタンパク質の存在状態が変化してクラスターを形成し、これをレクチン様分子が認識します。また、トロンボスポンジンがアポトーシス細胞に結合すると、マクロファージ表面のCD36やインテグリンαvβ3が認識することで貪食が促進されます。ただし、ネクローシス細胞においてもPSの外側露出が観察される場合があるため、細胞死の種類を正確に判別するには複数のマーカーを組み合わせた評価が必要です。
promega+1
臨床における細胞死の役割と新規治療戦略
アポトーシスとネクローシスの理解は、多くの疾患の病態解明と治療戦略の開発に直結します。がん細胞では、アポトーシス経路の異常(抗アポトーシスタンパク質の過剰発現やプロアポトーシスタンパク質の発現低下)により、細胞死に対する抵抗性を獲得していることが知られています。このため、アポトーシス経路を標的とした抗がん療法の開発が進められており、がん細胞の選択的な除去を目指した治療戦略が注目されています。
pmc.ncbi.nlm.nih+1
一方、炎症性疾患においては、ネクロプトーシスが病態の進展に重要な役割を果たしていることが明らかになっています。乾癬などの炎症性皮膚疾患では、角化細胞におけるRIPK1とMLKLの発現上昇が報告されており、ネクロプトーシスを標的とした治療が有効である可能性が示されています。また、筋細胞のネクロプトーシスが炎症性筋疾患の病態に関与することが示唆されており、RIPK1阻害剤などの治療的介入が検討されています。
tmd+1
筋細胞のネクロプトーシスを標的とした炎症性筋疾患治療の研究(東京医科歯科大学)
炎症性筋疾患におけるネクロプトーシスの役割と、その阻害による治療効果に関する重要な研究成果が報告されています。
虚血性疾患においては、血流遮断による組織のネクローシスが主要な病態ですが、再灌流時には酸化ストレスにより二次的なアポトーシスやネクロプトーシスが誘導されることが知られています。椎間板変性疾患においても、ネクロプトーシスが髄核細胞の死と炎症反応に寄与することが示されており、RIPK1/RIPK3/MLKL経路の阻害が治療標的となる可能性があります。
pubmed.ncbi.nlm.nih+2
PANoptosisと細胞死様式の統合的理解
従来、アポトーシス、ネクロプトーシス、パイロトーシスは独立した細胞死様式として理解されてきましたが、近年の研究により、これらの細胞死経路には複雑なクロストークが存在することが明らかになっています。2019年にKanneganti教授らによって提唱された「PANoptosis」は、pyroptosis、apoptosis、necroptosisの頭文字を取った概念で、これら3つの細胞死が同一細胞集団において同時に生じる現象を指します。
pmc.ncbi.nlm.nih+3
PANoptosisでは、「PANoptosome」と呼ばれる分子プラットフォームが形成され、ZBP1、RIPK1、RIPK3、カスパーゼ-1、カスパーゼ-8、NLRP3、ASC、FADDなど、複数の細胞死経路に関与する分子が同時に動員されます。この統合的な細胞死機構は、細菌やウイルス感染に対する生体防御において重要な役割を果たし、がん、感染症、無菌性炎症などの多様な疾患の病態に関与することが示されています。
pmc.ncbi.nlm.nih+3
PANoptosisの概念は、従来の細胞死分類の枠組みを超えた、より包括的な細胞死理解を提供します。細胞が受ける刺激の種類や細胞内環境に応じて、アポトーシス、ネクロプトーシス、パイロトーシスの要素が異なる割合で混在し、最終的な細胞の運命が決定されると考えられています。この動的な細胞死制御機構の解明は、疾患治療における新たな標的分子の同定につながることが期待されています。
pmc.ncbi.nlm.nih+2
PANoptosisに関する包括的レビュー論文(St. Jude Children's Research Hospital)
パイロトーシス、アポトーシス、ネクロプトーシスからPANoptosisに至る、プログラムされた細胞死経路の包括的なメカニズムが詳述されています。
| 細胞死の種類 | 制御機構 | 細胞膜の状態 | 炎症反応 | 主要な分子 |
|---|---|---|---|---|
| アポトーシス | プログラムされた細胞死 | 保持される | 誘発しない | カスパーゼ-3、-8、-9 |
| ネクローシス | 偶発的細胞死 | 早期破裂 | 強く誘発 | DAMPs(HMGB1、ATP) |
| ネクロプトーシス | 制御されたネクローシス | 早期破裂 | 誘発する | RIPK1、RIPK3、MLKL |
| パイロトーシス | 炎症性細胞死 | 破裂 | 強く誘発 | カスパーゼ-1、GSDMD |
細胞死研究の進展により、アポトーシスとネクローシスという二分法的理解から、多様な細胞死様式の連続体としての理解へと移行しています。各細胞死様式の分子機構の解明は、疾患の病態把握のみならず、細胞死経路を標的とした新規治療法の開発に重要な基盤を提供します。医療従事者にとって、これらの細胞死機構の理解は、診断精度の向上や個別化医療の実現に不可欠な知識となっています。
jstage.jst+1
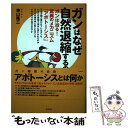
【中古】 ガンはなぜ自然退縮するのか ガンは治る!驚異のメカニズム「アポトーシス」 / 奥山 隆三 / 花伝社 [単行本]【メール便送料無料】【最短翌日配達対応】
