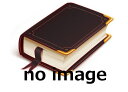アイソザイムの種類と分類
アイソザイムの遺伝的分類と構造
アイソザイムとは、同一個体内に存在し、同一の化学反応を触媒する酵素でありながら、タンパク質の分子構造が異なる複数の分子型で存在する酵素のことを指します。遺伝的観点から、アイソザイムは大きく三つの基本型に分類されます。
wikipedia+2
第一の分類は複遺伝子座位型(非対立遺伝子型)で、全く別の遺伝子に由来する狭義のアイソザイムです。第二は複対立遺伝子型(アロザイム)で、同じ種類の遺伝子でありながら配列がわずかに異なる対立遺伝子に由来します。第三は単一遺伝子型で、その他の機構により生成されるアイソザイムです。これらの遺伝的多様性により、アイソザイムは間接的な遺伝子マーカーとして集団遺伝学研究にも活用されてきました。
jstage.jst+1
アイソザイムの構造的特徴として、多くはサブユニットと呼ばれる単位タンパク質が複数結合した多量体として存在します。例えば乳酸脱水素酵素(LD)は4つのサブユニットからなる4量体構造を持ち、クレアチンキナーゼ(CK)は2つのサブユニットからなる2量体です。
falco+2
アイソザイムの主要な種類と臨床検査
臨床検査で測定される代表的なアイソザイムには、乳酸脱水素酵素(LD)、クレアチンキナーゼ(CK)、アルカリホスファターゼ(ALP)、アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(GOT)などがあります。
falco+3
LD(LDH)アイソザイムは、H型(Heart:心臓型)とM型(Muscle:筋肉型)の2種類のサブユニットからなり、その組み合わせにより5種類のアイソザイム(LD1からLD5)が存在します。具体的には、LD1(H4)、LD2(H3M1)、LD3(H2M2)、LD4(H1M3)、LD5(M4)という構成になっています。心臓、腎臓、赤血球は主にLD1・LD2を含み、肝臓や骨格筋はLD4・LD5を主成分とし、各組織で特異的なパターンを示します。sgs.liranet+3
CK(CPK)アイソザイムは、M(Muscle:筋肉型)とB(Brain:脳型)の2種類のサブユニットからなり、CK-BB、CK-MB、CK-MMの3種類が存在します。CK-BBは主に脳、子宮、腸管に、CK-MBは心筋に特異性が高く、CK-MMは骨格筋に多量に存在しますが臓器特異性は比較的乏しいという特徴があります。さらに、細胞内局在の異なるミトコンドリアCK(mCK)も知られています。sms+2
ALPアイソザイムは、肝性(L-ALP)、骨性(B-ALP)、胎盤性、小腸性などの数種類が存在し、それぞれ電気泳動易動度、耐熱性、各種アミノ酸による阻害パターンが異なります。犬ではコルチコステロイド誘発性(C-ALP)も認められます。falco+2
アイソザイムの測定方法と検査技術
アイソザイム分析法としては、主に電気泳動法が広く用いられており、その他に酵素阻害剤による活性の変化、分子量や等電点の測定、抗原抗体反応によるものなどが利用されます。
jstage.jst+1
電気泳動法には、アガロース膜電気泳動法、セルロースアセテート膜電気泳動法、等電点電気泳動法などがあります。アガロース膜電気泳動法は、LDアイソザイムやCKアイソザイムの分画測定に標準的に使用されており、IFCCによる標準化も進められています。等電点電気泳動法は、従来の電気泳動法とは異なり、分子の形や大きさの影響が少なく、等電点の差異によってアイソザイムを分離できる特徴があります。test-directory.srl+4
LDアイソザイム測定の基礎的検討では、泳動時間25分、脱色時間2分、検体塗布量4μLが最適条件とされています。測定における重要な注意点として、LD4・LD5は低温失活の影響を受けやすいため、凍結保存や4℃以下での保存は避ける必要があります。
kwtan.repo.nii+1
免疫学的測定法も開発されており、特にCK-MBの定量では、抗体を用いた免疫阻害法やCK-MBを蛋白として直接定量する方法が心筋障害の指標として測定されています。総活性測定と電気泳動法を併用して各アイソザイム活性を算出する場合、両者で同一の基質を使用し、各アイソザイムに対する反応性が同等となる条件設定が重要です。nitirinkyo+2
アイソザイムの臨床的意義と疾患診断
血清中の総酵素活性の上昇は多様な疾患で見られるため、特異性が低いという欠点があります。しかし、アイソザイム分画を分析することで、障害臓器の推定という点で臨床的に重要な意味を持ちます。
okayama-u+2
LDアイソザイムの臨床応用では、LD1・LD2の上昇は心筋梗塞、溶血性貧血、巨赤芽球性貧血で認められます。LD2・LD3の上昇は白血病やリンパ腫などの血液悪性腫瘍で見られ、LD5の上昇は急性肝炎や肝細胞癌の指標となります。このように、アイソザイムパターンの変化から疾患の種類や部位を推定することが可能です。yamauchi-iin+2
CKアイソザイムの診断的価値として、CK-BBは脳疾患、CK-MBは心疾患、特に心筋梗塞の早期診断に有用であり、CK-MMは横紋筋融解症や筋ジストロフィーなどの筋疾患の診断に使われます。細胞質分画のGOTとミトコンドリア分画のGOTの比率も、肝細胞障害の程度を評価する指標となります。tokyo-med+3
ALPアイソザイムの解析は、ALP高値の際に原因疾患を推定するために実施されます。ALP3分画は骨型ALPとして骨疾患の指標となり、肝型ALPは肝胆道系疾患の評価に用いられます。test-directory.srl+2
アイソザイムと発達段階・病態の関係
狭義のアイソザイムには、個体の発達に伴って比率が変化するものが存在します。例えば、乳児と成人とではアイソザイムの種類や比率が異なることが知られており、これは各発達段階における代謝機能の違いを反映しています。
toho-u+1
どの分子種(サブユニット組成)の割合が多いかによって代謝機能に微妙な変化が生じます。これは、同じ化学反応を触媒するアイソザイムであっても、それぞれ僅かずつ性質が異なるためです。このような性質の差異は、組織や細胞の代謝状態、エネルギー需要に応じた最適な酵素機能を提供するための生体の適応機構と考えられています。
toho-u
疾患によってもアイソザイムの比率が変化することが知られており、特に血液中の酵素では、疾患の種類によって特徴的なアイソザイムパターンの変動が観察されます。逸脱酵素であるLDは、組織が障害を受けた際に血中へ漏出し、そのアイソザイムパターンから障害組織を推定できます。
wikipedia+2
アイソザイムの分子生物学的研究と今後の展望
環状ヌクレオチドホスホジエステラーゼ(PDE)のアイソザイムファミリーは、生化学的性質から大きく5つに分類されています。それぞれのファミリーはさらに複数のサブファミリーに分けられ、I型PDEはCa2+/カルモジュリンにより活性化され、II型PDEはcGMPにより活性化されるなど、各アイソザイムが固有の機能を発揮しています。これらPDEアイソザイムの発現は、組織あるいは細胞ごとに異なっており、薬理学的な観点からも重要な研究対象となっています。
jstage.jst+1
アルドラーゼアイソザイム遺伝子の研究では、同遺伝子の高次構造(クロマチン構造)やDNAメチレーションと発現の相関について調べられており、組織特異的な発現調節機序の解明が進められています。このような分子生物学的研究により、アイソザイムの発現制御メカニズムが遺伝子レベルで明らかになりつつあります。
kaken.nii
現在では、アイソザイム分析に代わって、より直接的に目的の遺伝子DNAまたは遺伝子マーカーを調べる分子分類学やDNA鑑定などの手法が発展しています。しかし、臨床検査におけるアイソザイム測定は、迅速性、簡便性、コスト面から依然として重要な診断ツールとして位置づけられており、血液生化学検査の基本項目として広く実施されています。
falco+3
📊 アイソザイム検査の比較
| 酵素名 | アイソザイム数 | 主な種類 | 主な臨床的意義 | 測定方法 |
|---|---|---|---|---|
| LD(LDH) | 5種類 | LD1~LD5 | 心筋梗塞、肝疾患、血液疾患の鑑別falco | アガロース膜電気泳動法falco |
| CK(CPK) | 3種類 | CK-BB、CK-MB、CK-MM | 心筋梗塞、脳疾患、筋疾患の診断falco | アガロース膜電気泳動法、UV法sms |
| ALP | 複数種類 | 肝型、骨型、胎盤型、小腸型 | 肝胆道疾患、骨疾患の鑑別falco | 電気泳動法falco |
| GOT | 2種類 | GOTs(細胞質型)、GOTm(ミトコンドリア型) | 肝細胞障害の程度評価tokyo-med | 免疫吸収法jstage.jst |
アイソザイム検査におけるアノマリー(異常パターン)として、酵素結合性免疫グロブリンが認められることがあります。その臨床的意義は不詳であり、特定の疾患との明確な因果関係は確立されていませんが、関節リウマチなどの膠原病や各種疾患で観察されることが報告されています。
crc-group
🔗 参考情報:乳酸脱水素酵素アイソザイムの詳細については、岡山大学病院臨床検査部の解説が参考になります。電気泳動で分離された血清中の乳酸脱水素酵素アイソザイムの分画測定が、血液、肝、筋、腫瘍性疾患、心筋梗塞などの診断上重要視されています。
https://www.okayama-u.ac.jp/user/kensa/kensa/kouso/ld_iso.htm