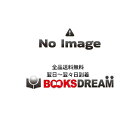再生不良性貧血と白血病の違い
再生不良性貧血の病態:造血幹細胞の傷害と機能不全
再生不良性貧血は骨髄の造血幹細胞が何らかの障害を受けて減少し、白血球・赤血球・血小板のすべてが減少する疾患です。血球自体の機能は正常で、数だけが減ってしまう点が特徴的です。国内では年間約1,000人が新たに発症し、全患者数は約5,000人とされています。
ubie+4
発症メカニズムとして、免疫学的機序による造血幹細胞の傷害が最も重要と考えられています。具体的には、Tリンパ球の異常活性化により造血幹細胞が選択的に攻撃され、造血抑制性サイトカインの産生によって発症します。約7割以上は原因不明の特発性とされ、残りは薬剤・放射線・ウイルス感染などが原因の続発性に分類されます。
pmc.ncbi.nlm.nih+4
骨髄を調べると、造血組織の多くが脂肪に置き換わっており、血球産生がほとんど行われていない状態が確認できます。この造血不全により、貧血症状(動悸・息切れ・疲労感)、感染症状(発熱・易感染性)、出血症状(鼻出血・皮下出血・紫斑)が出現します。
nanbyou+3
白血病の病態:造血幹細胞のがん化と異常細胞増殖
白血病は造血幹細胞ががん化し、異常な白血球(白血病細胞)が骨髄内で無秩序に増殖する血液のがんです。白血病細胞が骨髄を占拠することで、正常な造血幹細胞が機能できなくなり、結果として赤血球・血小板・正常白血球が減少します。
ubie+2
白血病は進行速度により「急性」と「慢性」に、異常が生じる細胞系統により「骨髄性」と「リンパ性」に分類されます。急性白血病では未成熟な芽球が急激に増加し、症状の発現が速いのが特徴です。診断基準として、WHO分類では骨髄における白血病細胞(芽球)が全有核細胞の20%以上を占めることとされています。
hiki-clinic+4
症状は正常血球機能の喪失と白血病細胞の臓器浸潤の二つの原因により発生します。貧血症状(動悸・息切れ・疲労感)、感染症状(発熱・感染症の遷延)、出血症状(鼻出血・歯肉出血・皮下出血)に加え、脾臓や肝臓の腫大、骨痛、中枢神経症状(頭痛・嘔吐)などの浸潤症状も認められます。
mymc+1
再生不良性貧血と白血病の診断法の違い:骨髄検査が鑑別の鍵
再生不良性貧血と白血病はともに汎血球減少を呈するため、血液検査のみでの鑑別は困難です。鑑別の決め手となるのは骨髄検査であり、骨髄穿刺と骨髄生検によって診断が確定されます。
shinyuri-hospital+3
再生不良性貧血の診断では、骨髄検査で造血細胞の著明な減少と脂肪組織への置換が確認されます。国際診断基準では、ヘモグロビン10g/dL未満、好中球1,500/μL未満、血小板5万/μL未満の3項目のうち2つ以上を満たし、骨髄が低形成の場合に診断されます。骨髄細胞密度は通常著しく低下しており、造血面積が10%未満となることもあります。
pmc.ncbi.nlm.nih+5
一方、白血病の診断では骨髄中に芽球(白血病細胞)が20%以上存在することが必要です。骨髄は通常過形成を示し、異常な芽球が骨髄を占拠している所見が得られます。ペルオキシダーゼ染色や細胞表面マーカー検査により、白血病細胞が骨髄系かリンパ系かを判定し、染色体・遺伝子検査で詳細な病型分類を行います。
jshem+4
MRI検査も有用で、再生不良性貧血では広範囲での骨髄の低形成状態を画像で確認できます。急性白血病との鑑別において、異常細胞の有無を確認することで容易に両者を区別できます。
kyowakirin+3
再生不良性貧血と白血病の治療法の相違点
再生不良性貧血の治療は免疫抑制療法が中心となります。具体的には、シクロスポリンやATG(抗胸腺細胞グロブリン)などの免疫抑制薬を使用して、造血幹細胞を攻撃しているTリンパ球を抑制し、造血機能の回復を図ります。免疫抑制療法後には約7割が輸血不要となるまで改善し、9割近くの長期生存が期待できます。
ubie+3
追加療法として、トロンボポエチン受容体作動薬(エルトロンボパグ)が造血幹細胞に直接作用して血球増加を促進します。支持療法では顆粒球コロニー刺激因子(G-CSF)が好中球減少に対して使用されます。40歳未満でHLA適合同胞ドナーがいる場合は、造血幹細胞移植が第一選択となることもあります。
jstage.jst+2
白血病の治療は多剤併用化学療法が基本です。急性骨髄性白血病では寛解導入療法で白血病細胞を1/100~1/1000に減少させて完全寛解を目指し、その後地固め療法で残存白血病細胞をさらに減少させます。急性リンパ性白血病では寛解導入療法、地固め療法に続いて、約2~3年間の維持療法を外来で継続します。
ubie+1
予後不良群や再発症例では同種造血幹細胞移植が考慮されます。移植前に強力な化学療法や全身放射線照射で白血病細胞を減少させ、HLA適合ドナーからの造血幹細胞を移植することで、ドナー細胞による抗白血病効果(GVL効果)も期待できます。慢性骨髄性白血病ではチロシンキナーゼ阻害薬が劇的な効果を示し、治療の中心となっています。
oshiete-gan+2
再生不良性貧血から白血病への移行:臨床的に重要な経過観察
再生不良性貧血の一部の症例では、経過観察中に骨髄異形成症候群(MDS)や急性骨髄性白血病に移行することが知られています。この現象は臨床的に重要な問題であり、長期フォローアップが必要とされます。
kyoto-u+3
京都大学の研究によれば、再生不良性貧血患者の約半数で経過中に白血病その他の血液がんで認められる遺伝子変異を持った細胞が出現します。これらの変異の約75%はPIGA、BCOR、BCORL1、DNMT3A、ASXL1の5つの遺伝子に生じます。
kyoto-u
特にDNMT3A、ASXL1変異を有する患者では、これらの変異細胞が経時的に増加して白血病を発症し、予後不良の傾向が認められます。一方、PIGA、BCOR、BCORL1変異を有する患者では、変異細胞が消失する傾向があり予後も良好です。中国の臨床研究では、再生不良性貧血から骨髄異形成症候群/急性骨髄性白血病へ移行した症例の多くで7番染色体モノソミーなどの染色体異常が確認されています。
pmc.ncbi.nlm.nih+1
移行のリスク因子として、長期のG-CSF使用や特定の染色体異常の出現が挙げられます。そのため、再生不良性貧血患者では定期的な骨髄検査と染色体・遺伝子検査によるモニタリングが重要です。早期に白血病への移行を検出することで、適切な治療介入のタイミングを逃さないようにする必要があります。
zoketsushogaihan.umin+3
再生不良性貧血における遺伝子変異の解明と白血病発症リスクに関する京都大学の研究報告
難病情報センターによる再生不良性貧血の診断・治療に関する詳細な情報