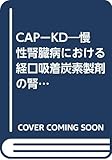ランダム化比較試験の例と基本
ランダム化比較試験の代表的な臨床例
ランダム化比較試験(RCT)は医療現場で多様な形で実施されています。最も基本的な例として、がん患者を対象とした新薬の効果検証試験があります。この試験では、がん患者が新薬群とプラセボ群のどちらに割り付けられるかが完全にランダムに決定され、患者自身の希望や医師の判断は介入しません。
参考)ランダム化比較試験とは?例を使って無作為化のメリットデメリッ…
整形外科領域では、前十字靭帯再建術後の患者に対する認知運動課題の効果を検証する準ランダム化比較試験が実施されています。また、脳卒中リハビリテーション分野では、ロボットスーツHALを用いた歩行練習の適応症例やQOLへの効果を検討するランダム化比較試験が行われました。
大腿骨頸部・転子部骨折症例に対するエルカトニン投与が術後リハビリテーションに及ぼす影響についても、ランダム化比較試験によって検証されています。
参考)前十字靭帯再建術後症例に対する認知運動課題が 膝関節位置覚に…
消化器内科領域では、大腸内視鏡検査におけるリドカインの腸管蠕動抑制効果を評価する多施設共同二重盲検ランダム化比較試験が実施されました。健康増進の分野では、健康高齢者に対する予防的・健康増進作業療法プログラムの効果を検証するランダム化比較試験も報告されています。
参考)健康高齢者に対する予防的・健康増進作業療法プログラムの効果 …
ランダム化比較試験におけるプラセボと盲検法
プラセボ対照二重盲検ランダム化比較試験は、医学研究における「ゴールドスタンダード」として位置づけられています。この研究デザインでは、被験者を実薬群とプラセボ群にランダムに割り付け、被験者と治療担当医の双方が割付内容を知らない状態で試験を実施します。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3505292/
二重盲検法の重要性は、1980年代のCAST試験によって明確に示されました。盲検化により、被験者が実薬を受けていると知ることによる過大な効果報告や、副作用への過度な心配による偏った有害事象報告を防ぐことができます。プラセボ対照試験において、被験者は自分が飲む薬が実薬かプラセボか分からない状況に置かれ、均等割付(1:1)の場合、実薬を受ける確率は50%となります。
参考)https://pharmacist.m3.com/column/placebo/2545
興味深いことに、二重盲検下で投与されたプラセボと、効果があると偽って投与されたプラセボでは、得られる効果に差がないか、後者の方が劣る可能性が指摘されています。
片頭痛に対するリザトリプタンの研究では、プラセボであることが確実か不確実かにかかわらず、鎮痛効果に明確な差が認められませんでした。
ランダム化比較試験と他の研究デザインの比較
研究デザインには階層があり、エビデンスレベルの観点から整理されます。最もエビデンスレベルが高いのは、ランダム化比較試験の結果を統合したシステマティックレビューです。その次がランダム化比較試験、続いて非ランダム化比較試験、コホート研究、症例対照研究、記述研究の順となります。
参考)https://jeaweb.jp/files/about_epi_research/contest2016_2.pdf
コホート研究は、将来にわたって疾患の改善や悪化を観察し、その要因を明らかにする研究手法です。一方、症例対照研究は、がんの死亡者について過去にがん検診を受診していたかを調べる後ろ向きの研究です。これらの研究手法では、検診受診者の特性によるセルフ・セレクション・バイアスが紛れ込む可能性があります。
参考)直接的証拠
ランダム化比較試験の最大の利点は、ランダム化という手法によって介入群と非介入群における患者背景の偏りを防げることです。被験者を研究者の意思でランダムに2つの群へ振り分けることで、年齢や性別、生活習慣や社会経済的環境などの背景因子を均一にすることが可能となります。一方、コホート研究では曝露群と非曝露群への振り分けは患者自身の生活環境に依存し、研究者の意思は介在しません。
参考)https://www.kinpodo-pub.co.jp/kinpodowp/media/sample/sp1807-5.pdf
ランダム化比較試験における交絡因子とバイアス対策
交絡因子とは、介入変数と観測変数の双方に相関を持つ因子のことを指します。交絡因子が比較対象群の中で偏って分布していると、介入とは無関係な観測値の差が生じ、セレクションバイアスを引き起こします。例えば、体重が膝伸展筋力に影響する場合、身長も間接的に影響する可能性があり、これが交絡として推測できます。
参考)「交絡因子」は,なぜ「セレクションバイアス」を引き起こすか.…
ランダム化比較試験では、交絡バイアスをほぼ回避できると考えられています。無作為割付によって、既知・未知を問わず交絡因子が両群に均等に分布する確率が高まり、治療効果の正確な評価が可能になります。しかし、ランダム化比較試験以外の研究デザインでは交絡バイアスが存在すると考えられるため、マッチングや多変量解析などの統計手法で調整する必要があります。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/rigaku/44/6/44_44-6kikaku_Tsushima_Eiki/_pdf
交絡因子の偏りにより発生する観測結果への不均一な重み付けが、比較集団における母平均への推定誤差を引き起こすという点が、セレクションバイアスの本質です。ランダム化によって交絡因子を制御することは、信頼性の高いエビデンスを構築する上で極めて重要な要素となっています。
参考)バイアス bias - 一般社団法人 日本理学療法学会連合
ランダム化比較試験の実施方法:層別化とクラスター化
ランダム化比較試験には、研究目的に応じて様々な割付方法が存在します。層別ランダム化は、バランスをとりたい要因が複数ある場合に用いられる手法です。例えば、性別と年齢(65歳以上と65歳未満)で層別化する場合、65歳以上男性、65歳未満男性、65歳以上女性、65歳未満女性という4つの層を作り、各層内でランダム化を実施します。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/jspho/56/5/56_432/_pdf
層別ランダム化では、各層内でどちらかの群に偏らないよう、ブロックランダム化という手法がよく併用されます。ブロックランダム化とは、割付治療数の倍数を「ブロック」としてブロック単位で割付順序を決める方法です。例えば、新薬群と既存治療群にランダム化する場合、4例分のブロックサイズを選択すると割付順序の配列は6通り用意でき、その中からランダムに配列を選んで患者を順番に割付けます。
参考)医療統計:層別ランダム割付|ビーリンサイト|製品・安全性情報…
クラスターランダム化比較試験は、個人ではなく施設や地域といった参加者のグループ(クラスター)を単位としてランダム化する研究デザインです。この方法は、介入を患者個人に割り付けることが不可能または不適切な場合に使用されます。例えば、多数の施設が参加する研究で医療従事者に対する教育効果を検証する場合、施設ごとの割付であれば各施設で1種類の講習会で済むため効率的です。個人ランダム化では同じ施設内で異なる介入を受ける患者が生じますが、クラスターランダム化では施設内の患者全員が同じ介入を受けることになります。
参考)クラスター RCT(小山田隼佑)
動的割付(適応的ランダム化)には最小化法などがあり、それぞれの要因ごとの合計数でバランスを考える手法です。静的割付として単純ランダム化や層別ランダム化があり、新治療群と対照群の割付順序を試験開始前に決定しておきます。実務上は、患者登録時にElectric Data Capture(EDC)システムを用いて割付治療を決定することが多くなっています。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/eiyogakuzashi1941/65/5/65_5_255/_pdf
ランダム化比較試験の限界とリアルワールドデータの補完的役割
ランダム化比較試験は高度に管理された医療環境における治療の「有効性(efficacy)」を検証する一方、日常臨床における「有用性(effectiveness)」の評価には限界があります。RCTは厳格な選択基準により対象患者が限定されるため、得られた研究結果の一般化可能性、すなわち外的妥当性が劣るという課題があります。
参考)リアルワールドデータ(RWD)の重要性と実臨床での活用 リア…
難病、希少疾患、医療機器、手術などの領域では、疾患の重篤性や対象患者数の限界により、通常のRCTによる治療法開発が困難なことが多いのです。また、すでに社会で広く使用されている治療法についてRCTを実施すると、研究対象集団が偏り、結果の一般化が困難な研究となってしまうこともあります。
参考)https://www.jstage.jst.go.jp/article/rsmp/7/3/7_197/_pdf
リアルワールドデータ(RWD)を用いた研究は、RCTの反対命題として重要性が再認識されています。RWDは現実世界での医療実践に基づいており、患者数が多く幅広い人口統計学的特徴を持つため、より広範な人口における治療効果や副作用など、現実世界における患者の状態をより正確に反映できます。RWDからは治療の処方実態や医療資源の使用状況、費用対効果に関するデータも得られます。
参考)RWD 2:臨床試験データとの違い-RWDがもたらす新たなエ…
COVID-19パンデミック時には、既存治療の電子カルテデータを解析して効果を比較する研究が行われ、希少疾病などRCTが難しい領域でもRWD分析により治療選択のヒントが得られることが示されました。RCTは介入群と対照群を無作為に割り付けることで適応交絡を除外できるため内的妥当性が最も高いのに対し、RWD研究は外的妥当性に優れているという相補的な関係にあります。RCTとRWDを適切に組み合わせることで、医療の改善や新しい治療法の開発により大きく貢献することが期待されています。
参考)日本におけるリアルワールドデータの臨床疫学への活用を目指して…
参考リンク:ランダム化比較試験の基本概念と実施方法の詳細について
ランダム化比較試験とは?例を使って無作為化のメリットを解説
参考リンク:層別ランダム化とブロックランダム化の実践的な手法について
医療統計:層別ランダム割付の実際
参考リンク:クラスターRCTの特徴と適用場面について
クラスター RCT:個人ランダム化との違いと実施上の注意点
参考リンク:プラセボ対照試験と二重盲検法の重要性について
プラセボ対照試験とは|その必要性と実施上の留意点
参考リンク:RCTとリアルワールドデータの相補的関係について
リアルワールドデータ(RWD)の重要性と実臨床での活用
医薬品に関する臨床系論文の読み方 ランダム化比較試験からリアルワールドデータ研究まで